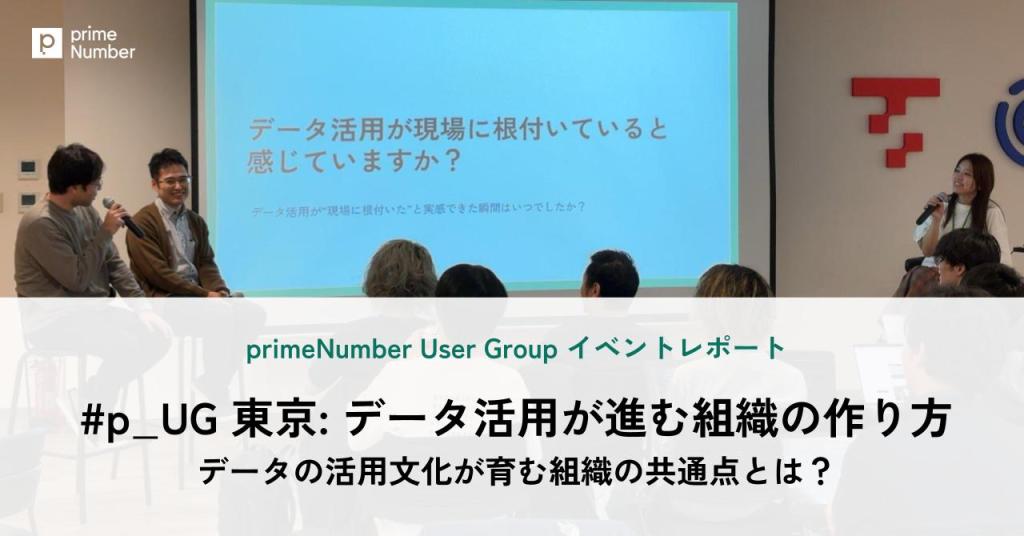2025年10月24日(金)primeNumber本社にて、primeNumber User Group(pUG)イベント「#p_UG 東京:データ活用が進む組織の作り方」が開催されました。
primeNumber User Groupとは
データ活用に取り組む参加者が相互交流し、それぞれの経験やノウハウを共有し合う場として運営されています。「TROCCO」や「COMETA」というツールの範疇を超え、データドリブンをいかに組織に浸透させるかといった組織的な課題の解決方法や具体的な製品のユースケース、データ活用の経験談を共有できる場として展開しています。
「日本のデータマネジメント領域のリーダーを増やす」をビジョンに、参加者とともに学び、盛り上げていくことを目指しています。本イベントはconnpassからお申し込みいただくだけで、既存ユーザーの方以外の方もご参加いただけます。
本イベントでは、TROCCOとCOMETAの最新アップデートに続き、「データ活用が進む組織の作り方」をテーマとしたパネルディスカッションが実施されました。
今回は、そのイベントレポートをお届けします。
オープニング
イベントオープニングでは、Xポストのご案内、自己紹介タイムを行いました。
#p_UG のポストから当日の様子もご覧いただけます。また運営メンバーにポストまとめを作成していただきましたので、こちらもぜひご覧ください。
お隣の方との自己紹介タイムは、データマネジメント領域を学んだり、盛り上げたりする仲間を作っていただければと思い、毎イベントで実施しています。
TROCCO/COMETAアップデート
primeNumber プロダクトマーケティングマネージャー鈴木大介より、「TROCCO」と「COMETA」の最新機能が紹介されました。
資料
TROCCOの主なアップデート
- 環境管理機能:開発環境から本番環境へ円滑に移行できる機能がリリース
- CDC(Change Data Capture)データ転送:データベースの変更を元に差分だけを読んで、効率的に処理する機能
- 転送元としてPostgreSQL、転送先としてBigQueryがリリース
- データマート Databricks対応:Databricks内でのデータ加工までの一連の流れを、他のデータベースと同様に利用可能に
- 新規コネクタ追加・拡充:DB2 for LUWやSAP S/4のデータ転送など、エンタープライズ企業での利用が多い製品が対応
COMETAの最近のリリース
- 対話型AIアセット機能:内部的な動きがエージェンティックになり、対話の品質が上がり、データ探索に使いやすく
- Redshiftの連携:これまでBigQueryとSnowflakeのみ対応していたが、Amazon Redshiftに関してもネイティブな連携が可能に
- メタデータアクセスコントロール機能:データカタログとして使える機能
- ユーザーによって、どこまで見せるかを細かく制御可能に
地味便利機能のご紹介
- 接続情報の利用状況確認機能:接続情報(データ転送や加工時の設定)が、どこで使われているか、何件あるかなどが一覧で見られるようになり、棚卸しが容易に
- ワークフローのコメント機能:データ転送やデータマートの加工をタスクとして設定するワークフローの中で、タスク単位でコメントが入れられるように
- チームで開発している時、特殊な仕様などを書いておくことで使いやすく
デモの実施
- 環境管理機能:開発環境から本番環境への移行を容易にする機能
- 設定を作り、開発環境に紐付け、本番環境にデプロイする際に、権限管理のリソースグループ、接続情報、カスタム変数(devをprodにするなど) といった差分設定を行うことで、本番環境用のリソースを作成できる
- これによって、本番環境を壊さずに済む
- Self Hosted-Runner機能:TROCCOのデータ転送を、利用者が管理している環境(オンプレミスなど)で実行できる機能
- エンタープライズのお客様など、TROCCO外から接続が難しいポリシーがある場合でも対応可能
- Docker上に乗せて構築するため、AWS、Azure、オンプレミスなどどの環境下でも構築可能。
- 通常、TROCCOがお客様の環境にデータを取りに行きますが、Self Hosted-Runnerを使うと、お客様の環境の中でRunnerが動くので、外向きの通信のみとなり、セキュリティ面も担保
- COMETA メタデータアクセスコントロール機能:「チーム」というユーザーのまとまりを作って権限を紐付け、アクセス管理を実施
- プロジェクトレベル、データセットレベルなどで、許可/拒否を設定することができ、細かい権限制御ができるように
イベント告知
【パネルディスカッション】データ活用が進む組織の作り方
登壇者
- パネリスト
- Classi株式会社 伊藤 徹郎氏
- 株式会社ヤプリ 阿部 昌利氏
- モデレーター
- primeNumber User Group コミュニティマネージャー 北川 佳奈
自己紹介
伊藤 徹郎氏(以下、敬称略): 教育系の会社Classiでプロダクト本部の本部長を3、4年務めています。主に高校や中学校など学校向けにSaaSを提供しています。2010年頃のビッグデータと言われていた時代からデータに関わってきました。趣味で5冊本を執筆しており、『実践的データ基盤の教科書』などは多くの方に読んでいただいています。
阿部 昌利氏(以下、敬称略): 株式会社ヤプリに5年前からジョインし、現在、4人の組織の長を務めています。2011年にキャリアをスタートし、データ一本で来ました。ヤプリはノーコードでアプリを作れるサービスを提供しています。
Q1:データ活用は現場に根付いていると感じていますか?
阿部: 30点です。入社時が5点ぐらいだったとすれば、30点ぐらいまで伸びたという感覚です。根付いているかどうかの判断は、ビジネスのプロセスや仕事のワークフローに組み込まれているかで判断しています。それができている領域は、僕の見えている範囲のまだ3割ぐらいです。
例えば、営業さんの活動で、アプリの規模によって料金が変動する際、アップセルの相談を始めるタイミングをデータで判断しワークフローで送っている部分や、カスタマーサクセスのメンバーがお客様の利用状況を把握し、先回りして動いているところなど、RevOps(レベニューオペレーション)文脈がだいぶ進んでいます。
伊藤: 80点ぐらいですかね。現場を「社内」に限定すれば、もっと高くてもいいぐらいです。真の現場である「学校」ではまだ使えていないため、20点分を下げているという感覚です。 社内ではめちゃめちゃ使えています。私はよくデータとかダッシュボードを「天気予報」に例えるのですが、天気予報は傘を持っていこうかといった意思決定に使うためのものです。データやBIがその意思決定に使う状態、つまり「成功したBI」の状態に完全になっていて、新しい施策をする際にも必ずデータの定量的なエビデンスをつけて出すのが根付いています。みんなが当たり前のように使っているという意味で、私は高い点数をつけたいです。
Q2:データ活用を増やすための取り組みについて
【管理職と現場のどちらから攻めるか】
伊藤: 管理職は見ないです。まずは現場で「みんな使ってますよ」という状態を作り、「上司のあなたが使わないんですか」というプレッシャーをかけていくのが良いです。 一時期、データの民主化のため、社内のデータ活用のダッシュボードで誰が使ってないかバイネームで見えるようにしていました。丁寧なコミュニケーションをとりつつ、BIの権限を剥奪する可能性を示唆するなどし、「ちょっとアカウントをつけてください」となるようにじわじわと兵糧攻めをしました。
阿部: これまでの経験から、管理職だけから入っても継続して使われにくく、割とおもちゃになりがちと感じています。現場のマネジメントで使われるような形で展開していくのが、順当に行きやすいと思っています。
【具体的な取り組み】
伊藤:王道なところで言うと、研修を実施しました。
Tableauの研修を3日間使って実施しました。Tableau社(現Salesforce社)の方にも協力していただき、データを活用することで嬉しいこと、可視化のプロセスが大変であることを体感してもらう狙いがありました。続いて、SQL道場です。SQLのコンテンツを1級, 2級のような形で用意し、教えました。
また、亜種としては感謝を伝えるUniposというサービスで、データ基盤のマスコット「ソクラテス」の疑似アカウントを作り、データを活用している人にポイントを送っていました。これはブームになり、結果として活用推進の一つの要素になりました。真面目一辺倒だけでなく、ちょっと斜め上から切り込んでみると意外と刺さるかもしれません。
阿部: みんなが見たいデータを握ることが一番手っ取り早いと思っています。それぞれのビジネス領域で「これが見れたら助かる」というデータを、面白く加工して提供しています。 戦略的に取りに行くことはあまりないですが、誠実に頑張っていると、ポジション異動のタイミングなどで「これ面倒見てくれないか」と相談が来るようになりました。各組織でちょっとツールを触っている人たちと、あらかじめコミュニケーションを取って仲良くしていると、相談されやすいです。
【コミュニケーション環境の整備】
伊藤: データとかAIを活用する「雑談相談チャンネル」は、最初は発言が全くありませんでした。粘り強く、データにまつわることは「ここに相談すれば大丈夫」ということを何年もかけてやり続けると、「そこに行けばとりあえずなんとかなる」という状態が醸成されます。すぐ諦めずに粘り強くやるのが大事です。
阿部: うちも「#to-data」というSlackチャンネルがあり、何でも聞いてOKです。第一問目の質問は「好きな食べ物」に設定し、無駄なマッチングをするなど、ラフでカジュアルな雰囲気を醸成しています。
Q3:組織内でデータを当たり前にしていくために大事なこと、AI時代に変わるところは?
阿部: 大事なのは、やはり成功体験を作っていくことです。 現在、点数が低い組織に対しては、まずデータを綺麗にして集めていくところから愚直にやっています。 今後のAI活用について、お客さん向けのAnalyticsツールはAIに頼ろうと考えています。お客様自身がダッシュボードからネクストアクションを導き出せないという課題があるため、AIでうまく導けるように来年トライする予定です。
伊藤: 組織のアラインメントを整えていくことが大事です。目標(四半期、半期、1年)に確実に定量目標を入れることです。そこから各部署がどう貢献するのかを何年かけて聞き続けると、「最終的な全社の目標はスコアを上げることだ。自分たちは貢献していない」という状況が見えてきます。 Classiでは、チャーンレートを目標とし、それをモニタリングするヘルススコアの基準を常にウォッチし、日常の活動と最終的なスコアがリンクしていることを確認しています。 また、ビジョンに「データ・テクノロジーを活用する」という目標があり、トップの意思があったことも重要です。
【AI活用と既存BI】
伊藤: SQLを書かずに自然言語で利用状況を聞くと教えてくれるAIエージェントを社内で構築しましたが、営業はデータ活用初期に作った1枚ペラのシンプルなBIダッシュボードを使い続けています。 なぜなら、そのBIを印刷して学校に持って行き、先生と「この機能が使われていないのでもっと活用しましょう」という相談の道具として使えるからです。 欲しい答えがすぐ分かるというのが一番重要であり、シンプルなダッシュボードの利便性が現時点では勝っています。AIがそこまで組んで用意してくれるようになれば変わると思いますが、まだ技術的に難しいと考えています。
ここからはイベント応募時点でいただいた事前質問への回答をしていただきました。
Q4:経営陣を含めた会社のトップ層をどのように巻き込んでいけば良いか?
伊藤: 私自身はマネージャーになることを固辞し、結果的に社長を部長にして機能しない期間を経て、仕方なく自分がそのポジションについたという経緯があります。 結果として、データをちゃんと活用したら成果が出るので、正しく評価されれば出世します。腹を決めて自分がやる方が、コミットもしやすいし結果も出やすいです。 また、AI時代にデータ活用を「使いたくない」というトップがいるのなら、出て行った方が良い(環境を変えるべき)と思います。
阿部: 伊藤さんは、安易に受諾せず、何回かラリーがあったことで、お互いに役割やリスペクトが生まれた可能性がありますね。コミュニケーションやすり合わせの積み重ねが重要だと、今のお話を聞いていて思いました。
Q5:データ活用人材の育成・浸透についてされていることは?
伊藤: コンテンツは残していますが、最近は「留学制度」をやってます。組織移動を伴わない半年間のレンタル移籍のような形で、ソフトウェアエンジニアがデータプラットフォームチームの仕事を半年間行います。これにより、勘所が分かったり、コミュニケーションがスムーズになるという狙いがあります。留学した人がチームに吸収されることが多いですが、結果として社内で育成できています。
阿部: 他部門の活用推進者の育成として、SQL研修(クエリ研修)を実施しました。これまでの会社ではなかなか継続的な利用にまで至りにくかったのですが、今回は初めて成功しました。 成功要因は、それまで手作業でCSVを落としてExcelで頑張っていた人が、SQLによって作業が劇的に効率化されたことです。成功体験を積んだことで、その人がチームに広め、さらにAIを使って分析させるレベルにまで到達しました。 また、エンドユーザーから直接問い合わせが来る部署の人は、自分でデータを出せるようになると喜びます。
Q6:ビジネスサイドでの活用事例は?
阿部: 商談において、お客さんが稟議を通すために「こういうデータが欲しい」と求められることがあり、売上という意味では直接的に効いた一例です。
伊藤: 私は、アナリスト機能を集中的なデータ基盤組織に持たせるのを避けるため、アナリストを雇いませんでした。その結果、営業系のマーケティング本部の中に、データを活用するアナリストチームができ始めました。そこからビジネスアナリストが採用され、データ基盤とセットで動く状態が3年ぐらいかけてできました。 具体的な事例としては、チャーン分析があります。学校は年度ごとに脱落が一気に来るため、これを5年ぐらいかけて精度高く分析し、全社で約100名ほどが参加する報告会を実施しています。 日常のヘルススコアのモニタリングからチャーン分析まで、すべて線に繋がっているのが特徴です。使われないBIは「点」でしかありません。一連の活動の中をモニタリングできる要素が入っていると、活用の幅が広がります。
Q7:データ活用の費用対効果をどのように評価していますか?
伊藤: 厳密には評価していません。 Slackのようなコミュニケーションツールと同様に、「これがなきゃ業務が回りませんよね」となった時、費用対効果の検証は不要になります。Classiではすでにデータを活用しないと次の施策が回らない状況です。 ただし、学術期間との共同研究で論文や学会発表を行い、プレスリリースにするといった形で、活用成果の種を見せたり、研修などで社内の活用度が上がったタイミングで「効果出てます」と報告するなど、「うまいことやる」のが一番良いです。
阿部: ヤプリの場合、SaaS向けのAnalyticsツールを有償で売れるという側面があったため、最低限のラインまでは費用対効果を達成できました。その後の綱引きは「頑張る」という形です。
Q8:Excelなどの人間フレンドリーなデータセットが当たり前の企業で、AIフレンドリーなデータセットに切り替えていくためのマインドや取り組みは?
伊藤: 複雑なExcelは人間フレンドリーかという疑問はありますが、「真の企業のデータパイプラインはExcelの中にある」という言葉があります。人々がExcelを使うのは「そこでしかできないことがあるから」です。改造されたExcelが作られている時点で、データ基盤は敗北だと思った方が良い。 秘伝のタレを継ぎ続けない方が良い可能性もあるため、一度、Excelを無くしてみることを検討してもいいかもしれません。 また、AI活用が可能な時代に、「結局何やりたいんですか?」という前提を確認することが重要です。昔はExcelしかなかったが、今は様々な手段があるため、目的を再確認し、適切な手段を提案すべきです。
阿部: 分かりやすいExcelであれば、AIでも結構いけるはずです。AIは要約が得意なので、AIで有用な答えを返すための集め方をしたいならば、切り替えが必要になります。 「このデータだけAIに食わせられたら、こういう世界に行けるんだよ」という成功イメージを見せていければ、切り替えの最初の一歩になる可能性があります。
primeNumber DATA SUMMIT 2025のご紹介
最後は、primeNumber DATA SUMMIT 2025のご案内です。
【primeNumber DATA SUMMIT 2025概要】
- 日時:11月26日(水)
- 場所:高輪ゲートウェイコンベンションセンター
- 規模:キーノート、ユーザーセッション、スペシャルトークなど、全て合わせて約40セッション。56名の登壇者でお届けする大ボリュームとなる予定
【注目セッション10選(抜粋)】
- KADOKAWA社のコンポーザブルCDPへの刷新事例:サイバー攻撃がきっかけとなり、データ基盤を根本的に見直し、ハイブリッドクラウドからフルクラウドへ、オールインワンCDPからコンポーザブルCDPへと刷新した事例について、技術的な話を深掘りします。
- 星野リゾートでのDATA Saber育成を含めたデータ活用までの取り組み:全社員IT事業人材化というビジョンのもと、データ活用分析のノウハウを、人材がいない状態からいかに変革したのか。現場(ホテル側の従業員)を巻き込んで進める取り組みについて話されます。
- GA Technologiesでのデータ基盤活用事例:CDOの奥村氏のセッション。「データ基盤はコストセンターではなくプロフィットセンターになる時代」として、経営とデータをつなぐ戦略の作り方、業績へのインパクトや効率化の事例を経営者目線から解説します。
- コミックシーモアにおけるデータ基盤・AI活用事例:スタッフ一人ひとりが企画に携わる組織の中で、データ基盤とAIの活用(ユーザーのクラスタリング、作品へのタグ付け、内製化したレコメンド基盤など)について、パネルディスカッション形式でお届けします。
- マクアケ社のkintoneデータ活用事例:サイボウズ社の方と、kintoneのデータ活用事例について、パネルディスカッション形式でお話しします。
- サミーネットワークス社のCOMETA活用事例:COMETAをどのように活用しているのか、「COMETAがなかったら困る」状況になっている詳細を深掘りします。
- CTO・CDOが語る 全社推進に向けた駆動と次の一手:弊社のCTO鈴木とラクスルの藤門氏によるセッション。情シス側でのAI活用事例を話し、社内を巻き込む方法について議論します。
- Data Engineering Study:CCCMK 松井氏、Ubie 大木氏、リクルート 阿部氏、stable 宮崎氏によるパネルディスカッション。AI時代に、データエンジニアやアナリストのキャリア設計について、賞味期限の短いスキルと長く価値を発揮し続けるスキルについて議論します。
- ベースフード社のデータ・TROCCO活用事例:製造、在庫、配送、受発注、顧客、デジタルマーケティング領域といったすべてのデータをTROCCOを使って統合し、サプライチェーン全体の可視化に取り組んでいる詳細をお話しいただきます。
- 大阪ガスが取り組むデータ民主化:「大阪ガスが切り開くデータ民主化の2.0とTROCCOで解き放すデータ活用の可能性」。実践される生成AIとTROCCOの統合による自立型データ基盤について共有します。データ民主化を阻む壁についても深掘りいただきます。
【ネットワーキングパーティー】 本セッション終了後、招待制のネットワーキングパーティーを予定しています。

クロージングでのご案内
- TROCCO フリープラン:クレジットカード登録不要で、毎月2時間まで利用可能です。100種類以上(もうすぐ200近く)のコネクタが利用でき、最近も様々なものが追加され、幅が広がっています。
- Data Engineering Study:次回はprimeNumber DATA SUMMITでの出張版です。アフタートークで質疑応答なども予定しています。
- Data Engineering SummitData Engineering Summit(Findy社主催):11月6日(木)にオンラインで開催され、弊社のCEO山本も登壇させていただきます。
- pUG Slackワークスペース:オンラインの交流場としてオープンしております
- connpassページ最下部よりご参加ください
primeNumber User Groupイベントはどなたでもご参加可能
primeNumber User Groupイベントは、未契約のお客様もご参加いただけます。組織内でデータ活用を進めていきたいが、進め方がわからない、課題があるという方は是非お気軽にご相談ください!
これまでのイベント詳細はこちらからご覧ください。
また、過去資料はこちらよりご覧ください。
https://pug.connpass.com/presentation
今後もコミュニティイベントを開催いたしますので、ぜひお気軽にご参加ください!